私と妻は80年代から環境保護活動に関わってきましたが、考えてみると正に人々に「現実を共有」してもらいたいという願いで様々な取り組みをしてきたとも言えます。
それはどうしてかと言うと、立場の異なる人たちがひとつの現実を共有できないかぎり、そこに対話も理解も生まれず、対立だけが残るからです。人と人がつながるためには、この現実の共有が必要条件です。
その意味でジャーナリズムとメディア(報道)のパワーは圧倒的であり、恐ろしいほどの”現実”を創造することが可能です。しかし彼らが報道という一方的な手段を握っている限り、一般の人々と広く現実を共有し、つながるためには、メディアを支配する彼らとまず現実を共有することが必要です。
高木仁三郎さんは、反原発活動に生涯を捧げ、その途中でガンに倒れた国際的にも著名な市民原子力科学者です。彼の業績は残された素晴らしい著作物からも明らかですが、彼の主張が正面から主要メディアでとり上げられたことはありませんでした。反原発の旗手として、原子力の恐ろしさを現場の科学者として訴えたきた彼の目には、311は起こるべくして起きたことだったでしょう。
高木さんの警告を真摯に受けた私たちは、いわゆる低レベル放射線被曝(内部被曝)の健康への深刻な影響を訴えるために2006年アメリカのアーネスト・スターングラス博士を日本に招聘して各地で講演会を開催しました。スターングラス博士は肥田舜太郎医師に低レベル放射線の影響を最初に伝えた人です。議員会館で報道各社を招いて記者会見を行いましたが、主要メディアで記事にしたところは皆無でした。私たちは原子力村の圧倒的パワーにただただ立ちすくむだけでした。
311一周年を迎えて、やっとジャーナリストたちの態度に変化が起こりつつあります。
とくに目に留まったのは京都新聞が社説ではっきりと日本が脱原発の道をとるべきだと書いたことです。
また報道ステーションのSPエンディングで司会者の古舘伊知郎氏が原発報道への反省決意表明をしたと聞きました。
そして今日読んだ共同通信の編集委員が書いた記事がこころに残ったので、ここにそのまま転載します。連載コラム「3・11に思う-われわれ科学記者と呼ばれる集団は、市民科学者の声にどれだけ真剣に耳を傾け、どれだけそれを社会に発信してきただろうか」と題したこの記事によって、多くのジャーナリストが目覚め、現実を共有してくれることをこころから願います。
**************************
連載コラム:「原発の不都合な真実」
東京電力福島第1原発事故後の1年を生きた。この1年間、記者として、それ以前に一市民として、自分は一体これまで何をしてきのか、これから何をするべきなのだろうと自問する日々が続いている。あの日以降、恐らくすべての日本人が、震災と原発事故後の日本でどう生きるのか、という問いに直面しているのだろう。震災と事故からわずか1年しか経っていない中で、一人の記者が感慨などを公表することにさして意味があるとは思えないのだが、編集部からの依頼もあって、今、自分の心の中にあるものをつづってみた。(共同通信編集委員 井田徹治)
× × × ×
私が東京の本社の科学部に配属されたのは1991年のことだった。当時の驚きの一つは「××省は」「●●庁は」という役所を主語にした記事ではないと意味のある記事ではないと考え、膨大な額の国家予算を投じて進められる巨大科学技術関連の記事を、官庁やその研究機関の研究者の話を基に、その意義や成果の十分な検証なしに発信する記者クラブ詰めの記者たちが、自分の周囲にいかに多いかということだった。
原発の安全性や電源としての優位性に関する神話、再生可能エネルギーは役に立たないという神話。最近では、「世界各国で原子力ルネッサンスが始まった」という神話。原発事故によって明らかになったこれらの多くの「神話」の形成に、そんな科学記者たちの行動が一役買ったことを否定するのは難しい。
だが一方で、1990年代の初めは、環境保護運動や反核運動が世界的な盛り上がりを見せ、その担い手である市民団体と、それを支える「市民科学者」の存在が重要度を増してきた時期でもあった。当時の日本で、官製の科学研究とは一線を画し、市民の側に足場を置いた「市民科学者」の重要性を指摘したのが故・高木仁三郎さんであった。高木さんの発言や行動に強い感銘と影響を受け、市民団体や市民科学者による研究報告などが提供してくれる、粗削りではあっても先見性と批判精神に富み、官製情報とはまったく違った弱者の視点に立った情報はとても新鮮だった。だが、役所の情報を、先を争って探り、役所からのリークを受けては記事を書く科学記者はいくらでもいたが、市民科学者の声に真剣に耳を傾ける記者は当時、まだ少なかった。
個人的には、役所からの官製情報からは距離を置き、市民団体やそれと行動をともにする内外の科学者たちの姿、そこからの情報を可能な限り発信する努力をしてきたつもりだった。少なくとも官製情報を基にした原発の安全神話や「原発は安定供給に貢献する安価な電源だ」との神話の形成に直接加担するようなことを、ジャーナリストとしてやってこなかったという自負もあった。だが、事故後の今、どう考えてみても自分の努力は不足していたと思う。私は科学部記者として1995年の阪神大震災の取材にかかわった。高木さんは震災直後、日本物理学会誌での論文の中で、巨大地震の後に非常用ディーゼル発電機の起動失敗などの可能性を列挙し「メルトダウンから大量の放射能放出に至るだろう」と指摘していた。不勉強にして、この論文の存在を知ったのはずっと後になってからのことで、それを記事することもしなかった。結果的に原子力にまつわる多くの神話の形成に少なからず加担してきたことに今、大きな責任を感じ、自らを恥じている。
そもそもわれわれ科学記者と呼ばれる集団は、市民科学者の声にどれだけ真剣に耳を傾け、どれだけそれを社会に発信してきただろうか。G8サミットなどの国際会議や官庁の取材、スペースシャトルの打ち上げなどの巨大プロジェクトの取材に投じるリソースの100分の1でも、市民科学者の取材に割いてきただろうか。
日常の取材の中で、電力会社と一体不可分となった原子力の安全規制、インサイダーだけで決められる原発と石炭火力を極度に偏重するエネルギー政策、再生可能エネルギーの拡大を阻むさまざまな利権といった問題を記者として知り、原発開発には極めて批判的なことを言いながら、心の中のかなりの部分を原発の安全神話が占めていたのだと今になって思う。
「科学における貧困の最大の理由は、大抵は豊かだと思い込むためだ。科学の目的は、無限の英知への扉を開くことではなく、無限の誤謬にひとつの終止符を打ってゆくことだ」というのはドイツの劇作家、ブレヒトの傑作の一つ「ガリレオの生涯」の中の一節である。
事故以来、この一文章がずっと頭に中にある。われわれ科学記者は、実はさして根拠のないことが多い「科学の豊かさ」にばかり気を取られ、多くの誤謬を一つずつ提起し、それを正していこうとする市民科学者の地道な努力に目を向けることは少なかった。
日本の市民科学者は、欧米の市民科学者に比べて、極めて不利な立場に置かれている。欧米なら簡単に入手できるような基礎的な情報や統計が、日本では役所や企業の手に握られたまま公開されずにいる。税制や寄付制度などが理由となって、市民科学者を支える市民団体の財政は常に厳しい。
だが、原発事故とその後の政府の対応の混乱は、今の日本において「オルタナティブな知」を担う市民科学者の存在がいかに重要であるかをあらためて示した。市民サイドに立った科学者が提供するオルタナティブな知の活動の不十分さ、それに真摯に耳を傾ける政策決定者と彼らを巻き込んだオープンな議論の場の欠如、十分な経験と知識を基にそれらを正確に伝えるメディアの不在。原発事故後に明らかになったこれらの問題点は、単に原子力やエネルギーだけの問題ではない。
1999年、JCOの臨界事故を受け、高木さんは、がんに苦しむ病床で「原発事故はなぜ繰り返すのか」(岩波新書)という本を書いた。その中で高木さんは「原子力時代の末期症状による大事故の危険」が「先に逝ってしまう人間の心を最も悩ます」と記し、「歴史を見通す透徹した知力と、大胆に現実に立ち向かう活発な行動力」を持つよう、残された者に呼び掛けた。
残念ながらわれわれ、残された者の努力は明らかに不十分だったと言わざるを得ない。2度とこの過ちを繰り返さないために、市民科学者たらんとする研究者が生まれ育つ環境を整え、日本社会全体でそれを支える仕組みを作ること。それが大切だと思う。
2012/03/11



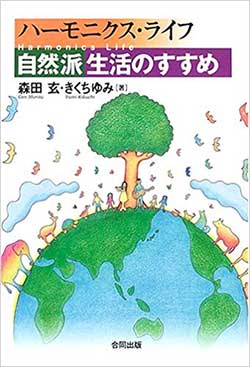





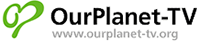

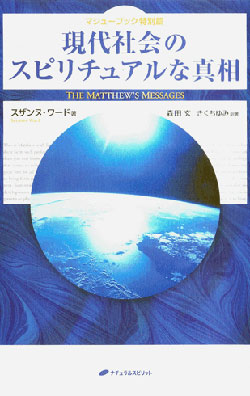






0 件のコメント:
コメントを投稿